怖いホラー小説というのは多くありますが、その怖さにはいくつかの種類がありますよね。
怪異現象やサスペンス、グロテスクなものなどは、物語を読む過程で、頭の中で非現実が形を成していく恐怖だと思います。
一方で、現実が壊れていくことで感じる恐怖というものもあります。今回紹介する『玩具修理者』に収録されている、『酔歩する男』という作品はまさにそれでしょう。
日本三大奇書といわれる『ドグラ・マグラ』的な恐怖とも言えるかもしれません。
『酔歩する男』は、あえてジャンル分けするなら、SFホラー小説、ということになるのでしょう。作品の舞台は現代で、未知のテクノロジーは出てこない。しかし、紛れもなくSF小説であり、疑いようもないくらいホラー小説なのです。
読み終えた後の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。読み終えた瞬間、まるで酔っ払ったような奇妙な酩酊感に襲われました。それまで信じていた現実が根底から揺らぐような感覚と、得体の知れない不安感がしばらく消えませんでした。
この記事では、なぜ『酔歩する男』がこれほどまでにわたしの心をゆさぶったのかを考えてみます。そして表題作『玩具修理者』も含めて、実際に読んだ感想と共にお伝えしていきます。
『玩具修理者』基本情報〜小林泰三デビュー作の概要
『玩具修理者』は、小林泰三さんが1995年に第2回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞したデビュー作で、表題作『玩具修理者』と中編『酔歩する男』の2編を収録した傑作ホラー短編集です。
角川ホラー文庫から刊行され、現在でも多くの書店で入手可能です。田中麗奈さん主演で映画化もされています。現在ではAudible版も制作されており、塩尻浩規さんの朗読で「聴く読書」としても楽しめます。
小林泰三さんは、理系出身の知識を活かし、「知的恐怖」という独特のジャンルを確立した稀代のホラー作家です。
京都府生まれで大阪大学基礎工学部出身、三洋電機ニューマテリアル研究所で開発者として勤務していたという理系バックグラウンドを持ち、多くの作品にそれが色濃く反映されています。
小林泰三さんの作品の最大の特徴は、感情的な恐怖ではなく「知的恐怖」を追求した点にあります。論理的に考えれば考えるほど恐ろしい結論に辿り着くという構造は、まさに理系出身ならではのアプローチでしょう。
2020年11月23日にがんのため58歳で逝去されました。本当に残念です。
広告
「酔歩する男」が圧倒的傑作である理由
中編「酔歩する男」は、量子力学の波動関数を利用したタイムトラベルという独創的な設定で、愛する人を救いたいという純粋な動機から始まった、絶望的な悪夢を描いた、SF的ホラー小説です。
読み終えた後、わたし自身が「酔歩する男」ではないかとの疑いを感じました。「現実とは何なのか」という根本的な疑問が頭の中をぐるぐると駆け巡り、自分が今いる世界すら信じられなくなる、そんな一種の混乱状態に陥ったのです。
量子力学が生み出すタイムトラベルの悪夢
この作品の最大の特徴は、従来のタイムトラベル作品とは一線を画す、絶望的な構造にあります。
一般的なタイムトラベル小説では「指定された時代に行ける」「死者や子孫に会える」「過去や未来を体感できる」といった希望的要素がありますよね。しかしこの作品に希望はありません。
まず「酔歩」という言葉について説明しましょう。これは数学や物理学で使われる「ランダムウォーク」のことで、次にどこへ向かうかが完全にランダムに決まる、予測不可能な歩き方を指します。酔っ払いがふらつきながら歩く様子に似ているため、こう呼ばれています。
物語では、この「酔歩」が二重の意味を持ちます。日常生活で軽い違和感や記憶の曖昧さに悩む現実の血沼(ちぬ)と、血沼の前に現れ、あらゆる時間や世界線を酔歩していると語る謎の男・小竹田(しのだ)です。
物語開始時の血沼の『酔歩』はそれほど重くはありません。普通の日常を生きていて、その中の小さな違和感が引っ掛かっている程度です。前に行った店にたどり着けない、あると思っていたものがない、ないと思っていたものがある、といった感じです。
そんな血沼の前に、小竹田という男が現れ、奇妙な話を始めます。
小竹田の語る世界では、血沼と小竹田は親友で、手児奈(てごな)という女性を取り合うライバルでもありました。ある日、手児奈は事故で命を落とします。愛する手児奈を失った悲しみは大きく、二人は彼女を救うための研究を始めます。
ここで物語は科学的な領域に入っていきます。二人が辿り着いたのは、量子力学の波動関数(物質の存在確率を表す物理学の概念)を利用した、極めて理論的なタイムトラベル方法でした。この方法では、人間の時間認識機能を意図的に破壊することで、時間の流れから解放された状態を作り出します。
しかし、この科学的アプローチによるタイムトラベルには恐ろしい代償がありました。二人はその実験の被検体となった結果、小竹田は時間や世界線を『酔歩』する存在となり、制御不能な悪夢の世界を生きることになったのです。
この二重構造が、血沼と、そして読者にも強烈な混乱と恐怖をもたらします。小竹田の語る物語は荒唐無稽なものですが、『酔歩』の感覚を知る血沼には響きます。小竹田の話を頭で否定しても、心の奥に染み込んでいく。現実と非現実の境界が崩れていく血沼を通して、やがて読者にも血沼の混乱が伝播していくのです。
わたし自身、物語のラスト近くでは「自分の持っている記憶が真実なのか?」と疑う気持ちが芽生えていました。それはまさに、主人公が体験している現実の揺らぎそのものでした。この作品の恐ろしさは、ページを閉じた後も続く、現実への不信感にあると思います。
広告
手児奈とはなんだったのか
この作品の中には最後まで解き明かされなかった謎があります。
それは、菟原手児奈という存在そのもの。
この不思議な響きの名を持った女性が物語の発端となっています。
小竹田と交際していたのですが、小竹田の暴走によって別れ、のちに血沼と交際を始める。それを認めない小竹田と血沼の間で諍いが起き、どちらかを選ばせる、というタイミングで手児奈はこの世を去ります。
自殺だったのか、事故だったのか。
実のところそれはどうでもよくて、謎は手児奈という存在そのものです。交際前の小竹田との会話には、手児奈という存在の不可解さがにじみ出ています。
現実的な解釈をすれば”不思議ちゃん”となるのでしょうが、SFホラーの文脈で読めば、時間を超越した、人ではない存在、といった気配が感じられます。
しかし、死後の彼女はいたって人間らしく、復活もしなければ夢枕に立ったりもしません。二人の男性を狂わせるためだけに存在したかのように感じられます。
『菟原処女伝説』という古典的伝承を下敷きにして編まれた作品のようですので、そちらをもっと深く調べれば、何らかの解釈が得られるのかもしれませんが・・・、Web検索程度では太刀打ちできませんでした。
広告
表題作「玩具修理者」の魅力と読みどころ
「酔歩する男」が好きすぎて後回しになってしまいましたが、表題作「玩具修理者」も間違いなく良い作品です。
シンプルな構造でありながら、読者に強烈なインパクトを与える手法は見事としか言いようがありません。
悪夢の童話としての完成度
この作品の真の恐ろしさは、その多層的な構造にあります。表面的には子どもの頃の不思議な体験談として語られますが、物語の結末で明かされる真実により、読者は全てを再解釈せざるを得なくなります。
物語は喫茶店での会話から始まります。室内にもかかわらずサングラスをかけた女性が、その理由を尋ねられて、子ども時代の不思議な体験を語り始めます。
近所に住んでいた玩具修理者は、子供たちだけが知っている秘密の存在で、壊れたおもちゃを何でも直してくれた、と。
女性の淡々とした語り口が歪さと純粋さを引き立て、グロテスクなシーンでも静謐さを感じさせます。
子どもの持つ、純粋・無知ゆえの、残酷で稚拙な発想も怖さの一因となっています。大人には理解できない子どもの論理が、この物語に独特の不条理さを与えているのです。
広告
クトゥルー神話要素の効果的活用
玩具修理者の名前「ようぐそうとほうとふ」は、クトゥルフ神話に登場する旧支配者「Yog-Sothoth(ヨグ=ソトホース)」から取られているらしいです。
作品中には他にも”くとひゅーるひゅー”(Cthulhu)、”ぬわいえいるれいとほうてぃーぷ”(Nyarlathotep)といった単語が登場し、独特の語感が不気味さを演出しています。
わたし自身は、小林泰三さんの作品に出合うまではクトゥルフ神話を知りませんでしたので意味は分かっていませんでしたが、不穏さだけは感じていました。
まとめ:これから読む人への注意点
『玩具修理者』は、「知的恐怖」という独特のジャンルを確立した歴史的意義を持つ作品です。『玩具修理者』に収蔵されている2作品を読み通せれば、小林泰三という作家の魅力を十分に理解できます。
「玩具修理者」はある程度のグロテスクさに対する耐性があれば問題ないと思いますが、「酔歩する男」は読者を選ぶ作品だと思います。
作中で語られる狂気は、引いて読んでしまうタイプの読者にはあまり響かないのではないかと思います。自分のことのように感じながら没入して読めるかどうかが重要なポイントだと思います。
しかし、この没入感というのは危険性も秘めています。
先に語ったように、この「酔歩する男」は現実感を揺さぶる作品です。地にしっかりと足がついている人なら多少揺さぶられても問題ないでしょうが、大きな悩みを抱えている人、自信を無くしていたりする人には刺激が強すぎるのではないかと心配になります。
心に余裕のある時に、どっぷりと浸ってほしい作品ですね。
なお、小林泰三作品では、2025年現在唯一Audible化されており、塩尻浩規さんの朗読で「耳で聴く読書」として楽しむこともできます。耳で聴く恐怖を体験したい方には、オーディオブックという選択肢もおすすめです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
🎧 Audibleで広がる読書体験 🎧
- 「ながら聴き」で時間を有効活用
家事や通勤、散歩中など、これまで「本が読めない」と思っていた時間を、Audibleがあれば有意義な読書時間に変えられます。 - プロのナレーターが織りなす、臨場感あふれる世界
まるで映画やドラマを見ているかのような、プロのナレーターによる迫真の演技と演出で、物語の世界に没頭できます。登場人物の感情や情景が、より鮮明に心に響くでしょう。 - オフライン再生で、いつでもどこでも読書を楽しめる
事前にダウンロードしておけば、電波の届かない場所でも、好きな時に読書を再開できます。
移動中や飛行機の中でも、読書の楽しみを途切れさせません。 - 再生速度の調整で、自分のペースで楽しめる
再生速度を調整できるので、効率的にインプットしたり、ゆっくり聴いて内容をじっくり理解したりと、自分のペースに合わせて調整できます。
広告

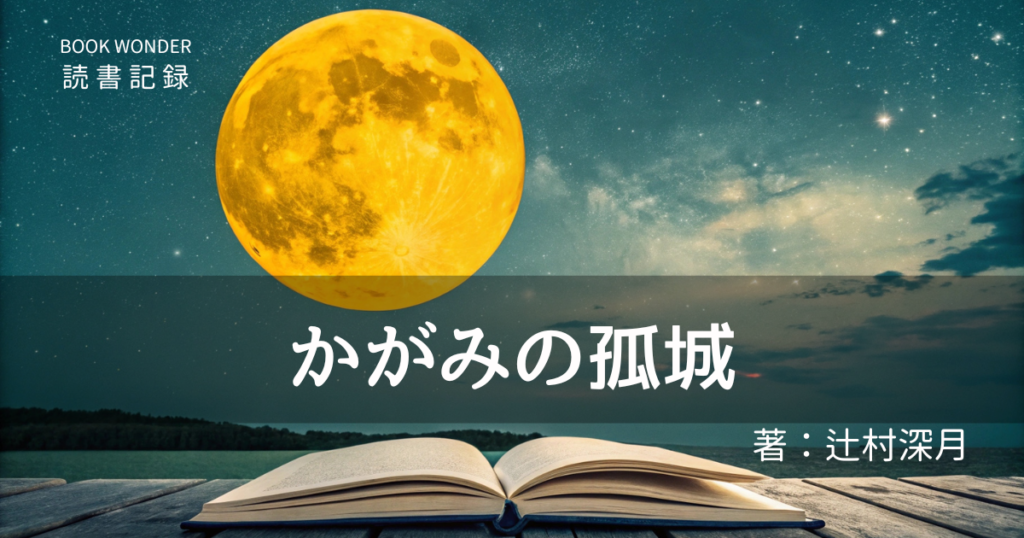

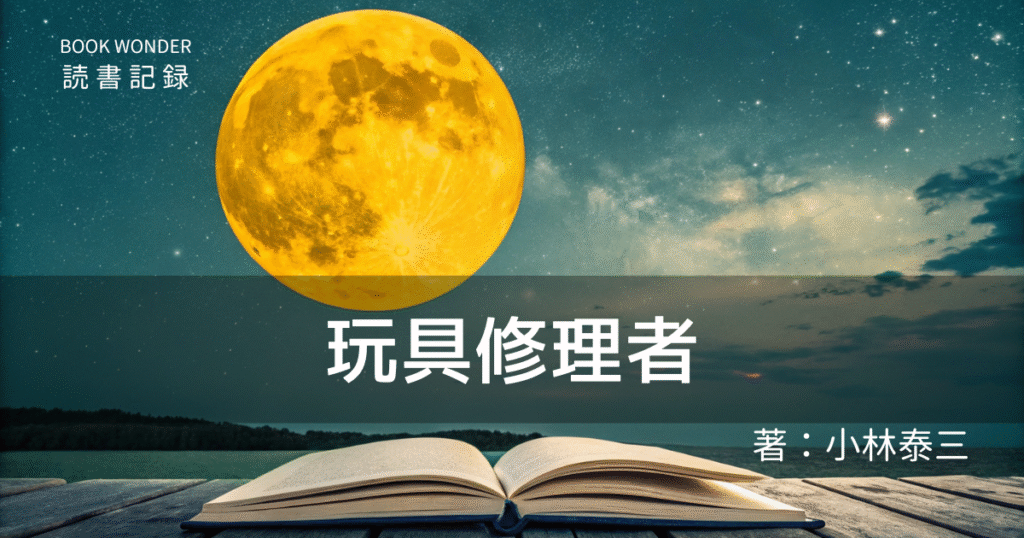
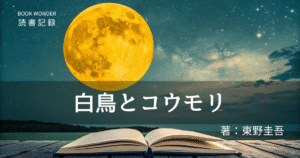
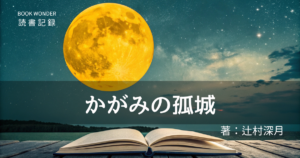
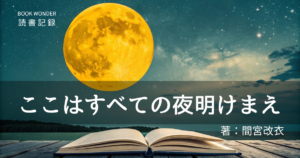
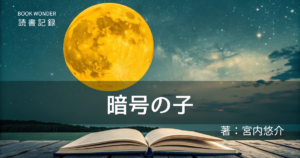
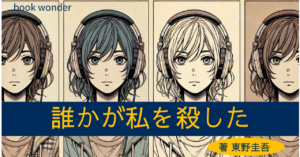

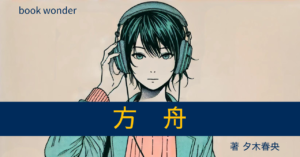
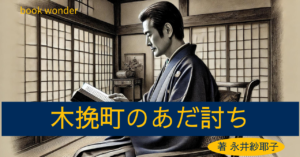
コメント