辻村深月さんの小説『かがみの孤城』は、表面上は同じ時代に生きる中学生たちの物語ですが、実は彼らは異なる年代に生きていました。
鏡を通して「孤城」に集う7人の中学生たちは、それぞれ1985年から2027年までの時代に生きていたのです。この特異な設定により、作品は日本の社会変化や子どもたちを取り巻く環境の変遷を浮き彫りにしています。
本解説では、各登場人物が生きていた時代背景と、その時代特有の出来事が彼らにどのような影響を与えたかを探ります。
登場人物と生きていた時代
スバルとアキの二人だけが昭和生まれであり、スバルは作品の中で「あと10年ちょっとで世界が終わるかもしれない」と考えていました。これは「ノストラダムスの大予言」に関するもので、2000年以降に生まれたフウカやウレシノには親しみのない話題です。
広告
時代背景と影響分析
1980年代:スバルの時代(1985年)
主な出来事
- 1983年:ファミコン発売
- 1985年:スーパーマリオブラザーズ発売
- 1989年:ゲームボーイ発売
スバルへの影響
スバルが中学生だった1985年は、ファミリーコンピュータ(ファミコン)がまだそれほど普及していない時代でした。スーパーマリオが発売されたばかりで、ドラゴンクエスト1は翌1986年の発売です。
スバルにとってのゲームは「新しい文化」であり、最新の娯楽として受け止められていたでしょう。
マサムネのようにゲームに没頭する環境ではなく、むしろ珍しい娯楽として接していたと考えられます。彼が孤城でマサムネのゲームに興味を示しつつも、その知識に乏しいのはこうした時代背景が影響しています。
また、スバルの紳士的な性格や物腰の柔らかさは、バブル経済前夜のまだ伝統的な価値観が色濃く残っていた時代の教育を受けた影響かもしれません。
広告
1990年代前半:アキの時代(1992年)
主な出来事
- 1990年:湾岸戦争
- 1990年:スーパーファミコン発売
- 1992年:第二土曜休み制度導入
- 1994年:プレイステーション発売
- 1995年:阪神淡路大震災
- 1995年:第二、第四土曜休み制度導入
アキへの影響
アキが生きた1992年は、学校週5日制が始まったばかりの時代です。第二土曜が休みになり、子どもたちの生活リズムが変わり始めた時期でした。
この時代はバブル経済崩壊後で、社会に閉塞感が漂い始めていました。
アキの快活さや強気な性格は、こうした社会の変化に抗うかのような逆説的な表れかもしれません。また、彼女がバレーボール部で後輩に厳しく接していたのも、まだ部活動での厳しい上下関係が当たり前だった時代背景が影響しているでしょう。
また、1995年に起きた阪神淡路大震災は、日本社会に大きな衝撃を与えました。この経験が彼女の人生観に影響を与え、後にフリースクールの先生として子どもたちを支援する道を選ぶきっかけのひとつになったのかもしれません。
広告
1990年代後半:ミオの時代(1999年)
主な出来事
- 1997年:ワンピース連載開始
- 1999年:ノストラダムスの大予言(世界終末説)
- 2000年:ハッピーマンデー制度導入
- 2000年:プレイステーション2発売
ミオへの影響
ミオは1999年3月30日に亡くなっています。この時代は、ノストラダムスの大予言で世界の終末が語られ、社会に不安が広がっていました。また、週休二日制度への移行期でもあり、学校や社会の制度が大きく変わろうとしていた時期です。
1999年という転換期に亡くなったミオが、過去と未来の子どもたちを繋ぐ役割を担っているのは、なんらかの意味があるのかもしれません。
2000年代中盤:こころとリオンの時代(2006年)
主な出来事
- 2001年:同時多発テロ
- 2002年:完全週休2日制導入
- 2004年:ニンテンドーDS発売
- 2006年:プレイステーション3発売
こころとリオンへの影響
こころとリオンが中学生だった2006年は、インターネットが徐々に普及し始め、携帯電話も子どもたちの間で広がり始めた時期です。しかし、まだSNSが今日ほど浸透していない時代であり、いじめの形態も現在とは少し異なっていました。
こころは従来型のいじめ(陰口や仲間外れ)で不登校になっていますが、この時代はネットいじめがまだ主流ではなく、実際の学校空間でのいじめが中心だったことが反映されています。
リオンが母親によってハワイに「厄介払い」されたという設定も、グローバル化が進む一方で、問題から逃れる手段として「海外」が使われるという当時の社会状況を反映しています。
PS3が発売された年でしたが、引きこもりのこころや海外にいるリオンにとって、それは話題にならなかったと作中で触れられています。
広告
2010年代:マサムネの時代(2013年)
主な出来事
- 2011年:東日本大震災
- 2011年:ニンテンドー3DS発売
- 2013年:プレイステーション4発売
- 2017年:『かがみの孤城』発売
マサムネへの影響
マサムネが生きる2013年は、スマートフォンやSNSが急速に普及した時代です。彼がゲームオタクであることや、ゲーム制作者との友達関係を嘘をついて自慢することで「ホラマサ」と呼ばれていじめられたという設定は、この時代のネット文化やゲーム文化の浸透を反映しています。
マサムネはゲーム好きの中学生として描かれていますが、作中で彼が所有しているのはプレイステーション(PS)2、3、そして「近々発売予定」のPS4です。2013年11月にPS4が発売されており、作中の時期と合致しています。
また、彼がポータブルゲーム機としてニンテンドー3DS(2011年発売)を持っていたことも描写されています。こころはこれを知らず、自分の知るニンテンドーDS(2004年発売)と混同しています。
東日本大震災の2年後という時期は、日本社会が復興に向かう一方で、子どもたちの心理にも影響を与えていた可能性があります。マサムネが現実逃避としてゲームの世界に没頭するのも、こうした時代背景が関係しているかもしれません。
また、彼の両親が「公立中学には通わせない」という方針を持っているのも、この時代の教育に対する不安や多様化する教育観が表れています。
マサムネの名前「青澄(あーす)」をウレシノが「キラキラネーム」と評しているのも、2000年代以降に増えた個性的な読み方の名前を表す言葉として使われ始めた「キラキラネーム」という表現が、2027年の時代には一般的になっていることを示しています。
広告
2020年代前半:フウカの時代(2020年)
主な出来事
- 2020年:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行
フウカへの影響
フウカが中学生だった2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大により世界が大きく変わった年でした。ただし、作品が2017年に発表されているため、作中のフウカの未来にはコロナ禍は存在しないと設定されています。
しかし、フウカがピアノに没頭する姿や、学校での人間関係の困難さは、現代の子どもたちが直面する「特定分野での才能育成と一般的な社会性のバランス」という問題を映し出しています。彼女の母親がピアノばかりに力を入れていることも、子どもの才能を伸ばそうとする現代の教育観の一側面を表しています。
2020年代後半:ウレシノの時代(2027年)
主な出来事
- 未来の設定のため、実際の出来事はまだ不明。
ウレシノへの影響
ウレシノは2027年という未来の時代に生きています。作中では彼の時代の具体的な特徴は描かれていませんが、「家が裕福で同級生に食事を奢るが実際は金づる程度にしか思われていない」という設定から、物質的な豊かさと精神的な貧しさのコントラストが描かれています。
彼の「恋愛気質で惚れっぽい」性格や、友人関係の希薄さは、未来社会における人間関係の変質を予見しているようにも読めます。SNSやバーチャル体験がさらに発達した未来で、リアルな人間関係を渇望する若者の姿が映し出されているのかもしれません。
広告
時代を超えた交流の意味
『かがみの孤城』において、異なる時代を生きる7人の中学生たちが孤城で出会い、交流することには深い意味があります。それぞれの時代で不登校やいじめなど似た問題に直面しながらも、時代背景によって異なる状況にある彼らが出会うことで、子どもたちの抱える問題の普遍性と特殊性の両方が浮き彫りになります。
特に注目すべきは、彼らが生きる時代が約7年ごとにずれていることです。この間隔は、世代間の断絶を表すと同時に、一つの世代が次の世代へとつながっていくサイクルも示しています。アキが成長してフリースクールの先生(喜多嶋先生)となり、こころたちを支える存在になるという展開は、世代を超えた支え合いの可能性を示唆しています。
また、オオカミさまの正体がミオ(リオンの亡くなった姉)であることも重要です。1999年に亡くなったミオが、過去と未来の子どもたちを「鏡」を通してつなぐ役割を担っているのは、記憶や絆が時間を超えて存在することを意味しています。
広告
学校制度と社会環境の変化
『かがみの孤城』では、約40年にわたる日本の学校制度や社会環境の変化が細かく描写されています。
学校の規模と制度の変化
登場人物たちが通う雪科第五中学校は、時代とともに規模が縮小していきます。
- スバルの時代(1985年):8クラス
- マサムネの時代(2013年):6クラス
- フウカの時代(2020年):4クラス
これは実際の日本の中学生人口の推移と一致しており、1985年には599万人だった中学生が、2005年には363万人、2018年には325万人と減少していることを反映しています。
また、学校制度も大きく変わっています。土曜日の授業に関しては、
- スバルの時代(1985年):毎週土曜日も授業がある
- アキの時代(1992年):第2土曜日が休みになり始めた時期
- こころの時代(2006年):完全週休2日制(2002年導入)
祝日の変更も描かれており、成人の日は2000年まで1月15日でしたが、ハッピーマンデー制度の導入により1月の第2月曜日に変更されました。スバルやアキはこの変化を知りません。
カレンダーの違い
物語の中で重要な「決戦の日」である1月10日は、各登場人物の時代で異なる曜日に当たり、学校の始業式かどうかも異なります。
| 名前 | 決戦の日 | 曜日 | 始業式 |
|---|---|---|---|
| スバル | 1985年1月10日 | 木曜日 | ○ |
| アキ | 1992年1月10日 | 金曜日 | ? |
| こころ | 2006年1月10日 | 火曜日 | × |
| マサムネ | 2013年1月10日 | 木曜日 | ○ |
| フウカ | 2020年1月10日 | 金曜日 | ? |
| ウレシノ | 2027年1月10日 | 日曜日 | × |
また、うるう年に関するエピソードも印象的です。2月29日には、その年がうるう年である時代の人物(アキとフウカ)だけが城に来ることができました。
広告
街の移り変わりと電子機器の変遷
商業施設の変化
- スバル・アキの時代:駅前や商店街が中心
- こころの時代:ショッピングモール「カレオ」が中心(1999年頃オープン)
- マサムネ・フウカの時代:より大規模なショッピングモール「アルコ」(映画館も併設)
食料品を販売する移動販売車「ミカワ青果」はアキやこころの時代には存在していましたが、フウカの時代にはなくなり、ウレシノの時代には再び別の形で移動販売が復活しています。
電子機器の進化
スバルが使っていたのはカセットテープを入れる「ウォークマン」(1979年発売)、アキは「ポケベル」で彼氏と連絡を取り合い、こころの時代には既に携帯電話が普及しています。また、「アドレス」という言葉の意味も時代によって異なり、スバルは「住所や電話番号」、フウカは「メールアドレス」と捉えています。
言葉の変化も見られ、「イケメン」や「超」といった表現はスバルの時代にはまだ一般的ではありませんでした。
広告
時代を超えた絆~喜多嶋先生の存在
物語の核心部分として、アキが成長して「喜多嶋晶子」となり、フリースクール「心の教室」の先生として、後の時代の登場人物たちと関わっていく設定があります。その時系列は以下の通りです:
- 1993年3月:晶子(アキ)中学卒業
- 1996年4月:大学入学、「心の教室」で手伝い始める
- 1998年:大学3年生で喜多嶋先生と出会い、ミオに勉強を教える
- 1999年3月30日:ミオ死去
- その後:大学院修了、喜多嶋先生と結婚
- 2005年度:29歳、こころと出会う
- 2012年度:36歳、マサムネと出会う
- 2019年度:43歳、フウカと出会う
- 2026年度:50歳、ウレシノと出会う
この設定により、時代を超えた循環的な影響関係が生まれています。例えば、フウカから「勉強はローリスク」という言葉を聞いた中学生のアキが勉強を始め、後に喜多嶋先生となってフウカに同じ言葉を伝えるという循環が描かれています。
『かがみの孤城』の伏線~ナガヒサ・ロクレン
マサムネが崇拝するゲーム『ゲートワールド』の開発者「ナガヒサ・ロクレン」は、実は大人になったスバルであることが示唆されています。スバルの本名「長久昴」と、昴(プレアデス星団)の別名「六連星(むつらぼし)」から「ロクレン」という名前が取られています。
スバルは「マサムネがゲームを作った友達がいると言えるように」と開発者になることを決意しており、その夢が実現されたことが示されています。
7人の未来での出会い
劇場アニメの追加映像や特典では、様々な形での再会が描かれています。
- アキ(喜多嶋先生)はスバル以外の全員と会っている
- こころとリオンは同時代の雪科第五中学で再会し、親交を深めている
- マサムネはスバルが開発したゲームを知っており、サイン会で会っている
- コンサートでフウカが演奏するピアノをウレシノが聴いている
そして、7人(+オオカミ様)が一堂に会した奇跡も・・・。
まとめ
『かがみの孤城』は、1985年から2027年までの日本社会の変化を背景に、それぞれの時代を生きる中学生たちの物語を通して、不登校やいじめといった問題の普遍性と、時代によって変化する特殊性の両方を描き出しています。
時代によって変わるもの(技術、言葉、街の風景、学校制度)と変わらないもの(思春期の悩み、人との繋がりの大切さ)を対比させることで、作品は「時代を超えた絆」というテーマを鮮明に描き出しています。
孤城という超越的な空間で時代を超えて出会った彼らが、それぞれの時代に戻っても、その記憶は完全には消えず、何らかの形でつながっていくという物語の結末は、時代を超えた人と人との絆の可能性を示唆しています。それはまた、異なる世代間の理解と共感の大切さというメッセージでもあるのです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
🎧 Audibleで広がる読書体験 🎧
- 「ながら聴き」で時間を有効活用
家事や通勤、散歩中など、これまで「本が読めない」と思っていた時間を、Audibleがあれば有意義な読書時間に変えられます。 - プロのナレーターが織りなす、臨場感あふれる世界
まるで映画やドラマを見ているかのような、プロのナレーターによる迫真の演技と演出で、物語の世界に没頭できます。登場人物の感情や情景が、より鮮明に心に響くでしょう。 - オフライン再生で、いつでもどこでも読書を楽しめる
事前にダウンロードしておけば、電波の届かない場所でも、好きな時に読書を再開できます。
移動中や飛行機の中でも、読書の楽しみを途切れさせません。 - 再生速度の調整で、自分のペースで楽しめる
再生速度を調整できるので、効率的にインプットしたり、ゆっくり聴いて内容をじっくり理解したりと、自分のペースに合わせて調整できます。
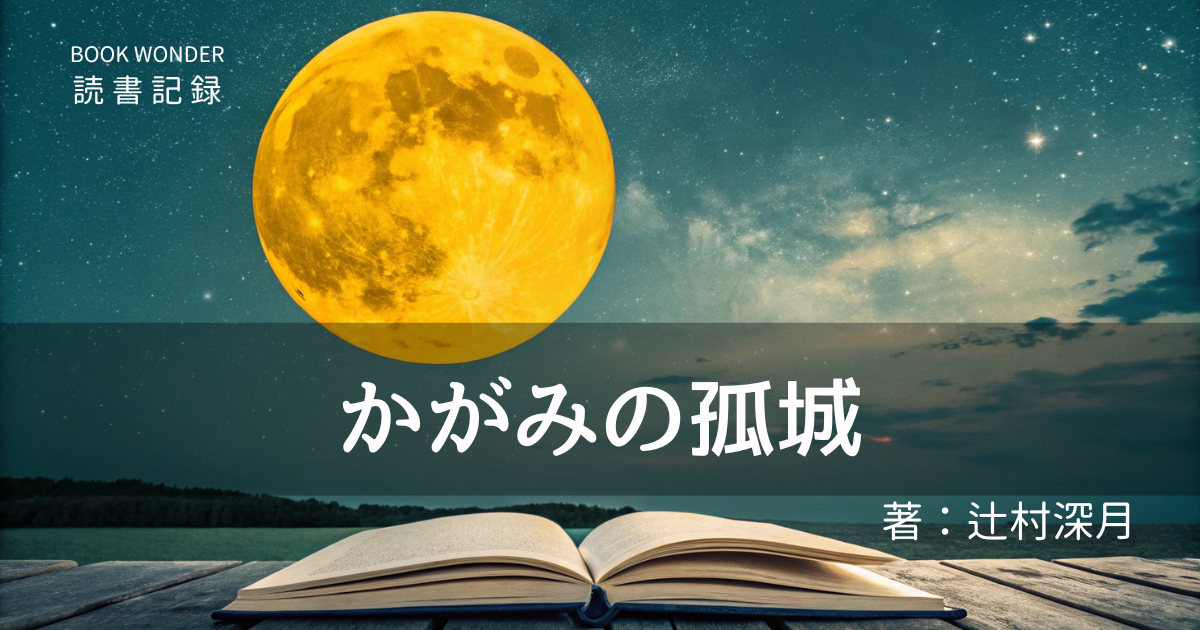
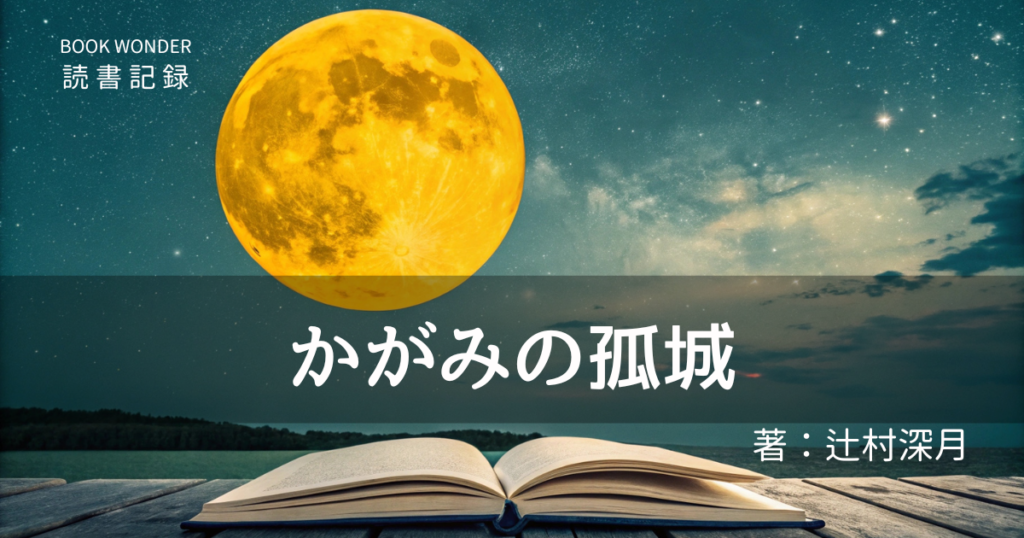

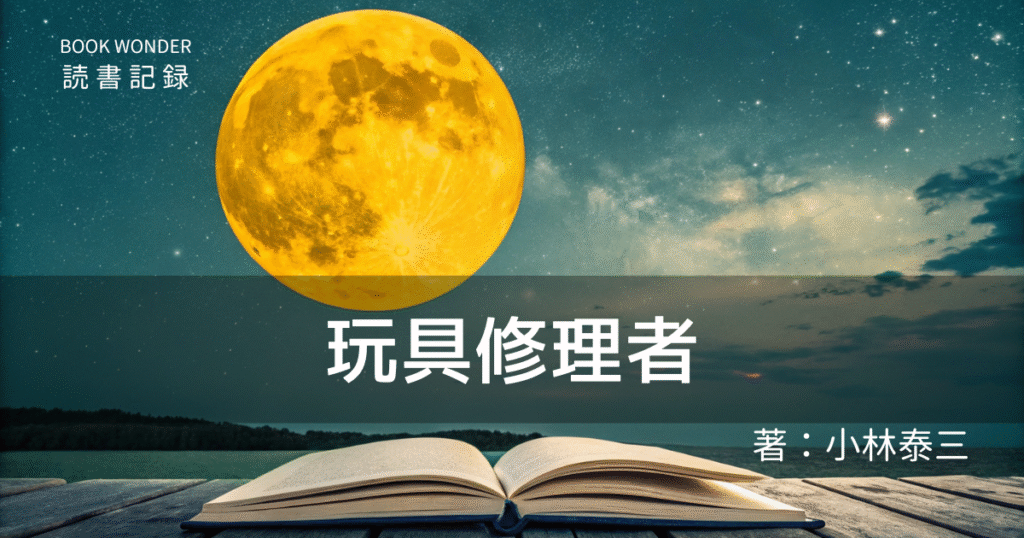
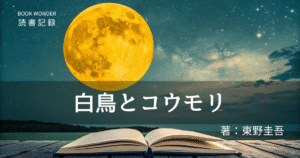
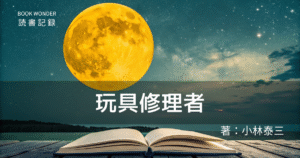
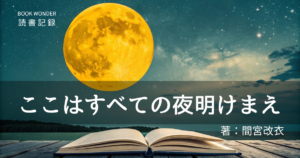
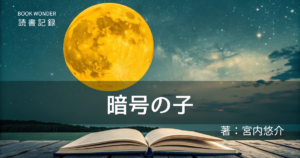
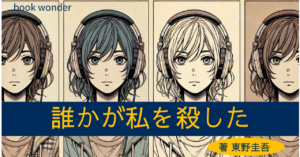

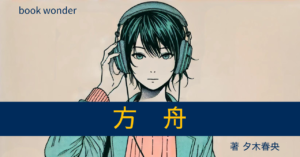
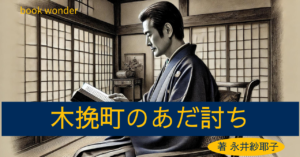
コメント